日本の近代音楽の基礎を作った/下總皖一の紹介
作曲家としての下總皖一
「たなばたさま」「花火」「野菊」「ほたる」などの曲は、下總皖一の曲として有名ですが、実は、彼の作曲分野は極めて幅広く、合唱曲、器楽曲、協奏曲や校歌など、多岐にわたっています。
また、箏の曲、三味線の曲など日本の伝統音楽についても作曲し、その数2,000曲とも3,000曲とも言われています。
音楽理論家としての下總皖一
昭和9年(1934)ドイツ留学から帰って、翌10年に著した理論書「和声学」は、ドイツでの恩師パウル・ヒンデミットから激賞されました。その後次々と理論書を著し、「作曲法」「日本音階の話」「作曲法入門」「楽典」「音楽理論」「対位法」など日本の近代音楽の基礎を作ったとされています。「和声学」の神様とも言われています。
音楽教育家としての下總皖一
東京音楽学校を首席で卒業した下總は、各地の学校で教鞭をとりました。女子師範学校・各地の師範学校・小学校・女子高等師範学校など。
また、留学から帰朝後は母校東京音楽学校で、東京芸術大学では音楽学部長をつとめるなど、数多くの俊英を育てました。
| 明治31年(1898年) | 3月31日、埼玉県原道村大字砂原75(旧大利根町)に父吉之丞、母ふさの二男として生まれる。 | |
|---|---|---|
| 明治45年(1912年) | 14歳 | 3月、栗橋尋常高等小学校高等科を卒業。 |
| 大正6年(1917年) | 19歳 | 3月、埼玉師範学校本科一部を卒業。(現・埼玉大学) |
| 大正9年(1920年) | 22歳 | 3月、東京音楽学校を首席で卒業。記念奨学賞を受ける。(現・東京芸術大学) 4月、長岡女子師範学校に赴任。 |
| 大正10年(1921年) | 23歳 | 1月、飯尾千代子と結婚。 9月、秋田県立秋田高等女学校へ転任。秋田県師範学校付属小学校にても教鞭をとる。この地で新居を構えた。 |
| 大正13年(1924年) | 26歳 | 9月、栃木師範学校に転任。千代子夫人病気がちのため伸枝と改名。下總も覚三改め、皖一を名乗る。本格的に作曲に取り組む。 |
| 昭和2年(1927年) | 29歳 | 4月、上京。居住を牛込喜久井町に移す。 |
| 昭和7年(1932年) | 34歳 | 3月21日、文部省在外研究員として、作曲法研究のため渡独。ベルリンの国立ホッホシューレに入学。パウル・ヒンデミット教授に師事。 |
| 昭和9年(1934年) | 36歳 | 9月3日、滞独2年の留学生活を終えて神戸港に帰着。東京音楽学校講師となる。 12月、助教授となる。 |
| 昭和10年(1935年) | 37歳 | 曲:三味線協奏曲 著:和声学 |
| 昭和13年(1938年) | 40歳 | 曲:箏独奏のためのソナタ 著:作曲法 |
| 昭和15年(1940年) | 42歳 | 文部省教科書編集委員となる。 |
| 昭和16年(1941年) | 43歳 | 9月、品川区上大崎に転居。 |
| 昭和17年(1942年) | 44歳 | 3月、東京音楽学校教授となる。 |
| 昭和19年(1944年) | 46歳 | 著:日本音階の話 |
| 昭和25年(1950年) | 52歳 | 下總皖一混声合唱曲集10巻の出版始まる。 |
| 昭和30年(1955年) | 57歳 | 11月、文部省教科調査委員となる。 |
| 昭和31年(1956年) | 58歳 | 10月、東京芸術大学音楽学部長となる。 |
| 昭和33年(1958年) | 60歳 | 1月、東京国立文化財研究所芸能部長となる。 11月、文部省視学委員となる。 |
| 昭和34年(1959年) | 61歳 | 6月1日、東京芸術大学音楽学部長を辞任。教授として逝去まで同大学に在籍。 |
| 昭和37年(1962年) | 64歳 | 7月8日、胆石、肝臓ガン、肝硬変の悪化で他界。 |
「高く飛ぶ鳥は 地に伏すこと長し」
下總皖一は、若い人たちに向かって、いつもこの言葉を投げかけていました。
若いときにこそ、下積みの時代にこそ我慢をし、努力をし、実力を蓄えて、そして高く飛ぼうと。

若い頃の下總皖一

道の駅にある下總皖一の銅像
下總皖一資料コーナー
大利根文化・学習センター「アスタホール」内に下總皖一資料コーナーを設置しています。
下總が愛用していたピアノや肉筆の楽譜などの貴重な品や、校歌マップなどを展示しています。


この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習部 生涯学習課(パストラルかぞ内)
〒 347-0006
埼玉県加須市上三俣2255
電話番号:0480-62-1223 ファックス番号:0480-62-2221
メールでのお問い合わせはこちら





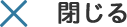

更新日:2024年08月08日