給食の味をご家庭でも!給食レシピを紹介します!
栄養士おすすめの学校給食レシピを紹介します。ぜひ、ご家庭でも作ってみてください。 下表のメニュー名(PDFファイル)をクリックし、ご覧ください。
令和7年度
第4回 みそポテト

みそポテトは、埼玉県のB級グルメとして有名になりましたが、実は秩父地方に古くから伝わる郷土料理の一つです。揚げたじゃがいもに、甘めのみそだれがよく合います。農家では、農作業の合間に食べる「小昼飯(こぢゅうはん)」として食べられてきましたが、現在では学校給食で提供されたり、スーパーのお惣菜で売られたりしています。簡単に作ることができるので、ぜひご家庭でも作ってみてください。
第3回 ジャーチャン豆腐(家常豆腐)

ジャーチャン豆腐(家常豆腐)は、中国の家庭料理のひとつで、「家常」には、「家庭でいつも食べられている」という意味があります。冷蔵庫にある野菜と豆腐を使った料理ということから名づけられました。
トウバンジャンが入るため、少しスパイシーな味付けがごはんにぴったりです。お好みの野菜をたっぷりと使って、ご家庭でも作ってみてください。
ジャーチャン豆腐(家常豆腐) (PDFファイル: 794.6KB)
第2回 ひじきのカレー炒め

和食に使用することの多いひじきですが、苦手な人でも食べやすいようにカレー粉を加えて味付けしています。
スパイシーな味が食欲をそそり、ご飯も進みます。ひじきには、成長期に欠かせない鉄やカルシウムなどが豊富に含まれていますので、ぜひご家庭でも作ってみてください。
第1回 米粉のクラムチャウダー

クラムチャウダーは、アメリカで生まれた料理です。「クラム」は英語で2枚貝のことを言い、「チャウダー」は魚介と野菜を煮込んだスープという意味があります。春が旬のあさりを使い、ホワイトルウや小麦粉でなく米粉を使ってとろみをつけました。
米粉のクラムチャウダー (PDFファイル: 478.8KB)
令和6年度
第4回加須産大豆のキーマカレー

加須市は、大豆の生産量が県内1位です。こどもたちにもっと親しみをもって欲しいという思いから、特産物の大豆をキーマカレーにしました。大豆を細かくひきわりにすることで、食べやすく、良質なたんぱく質が豊富なカレーになります。
加須産大豆のキーマカレー (PDFファイル: 472.3KB)
第3回 ホキの南蛮漬け

今回のホキの南蛮漬けは、9月、10月に給食で提供しました。ねぎをしっかりと炒めることで調味料がしみこんで、白身魚との相性はぴったりです。タレがかかって味がついていると、魚が苦手な子でも挑戦して食べてくれます。ぜひご家庭でも作ってみてください。
第2回 なす南蛮汁

加須市は、うどんの町です。今回のなす南蛮汁は、「加須市うどんの日献立」として6月の給食で提供しました。市内のうどん店でも、なすがたっぷり入った汁に、うどんをつけて食べる「なす南蛮うどん」は定番メニューです。
また、加須市は、なすの生産量が県内トップクラスで、給食でも地場産のなすを使いました。旬でおいしいなすを使って、ご家庭でも作ってみてください。
第1回 焼きフランクの香味ソースかけ

「ウィンナーソーセージ」や「フランクフルトソーセージ」、「ボロニアソーセージ」などソーセージには、ドイツやオーストリア、イタリアの都市の名前がついています。日本ではJAS規格で、太さ20ミリメートル未満のものを「ウィンナー」、太さ20ミリメートル以上36ミリメートル未満のものを「フランクフルト」、36ミリメートル以上のものを「ボロニアソーセージ」と決まっていますが、本場のドイツやオーストリア、イタリアには、こういった決まりがなく、全て「ソーセージ」と呼ばれています。
焼きフランクの香味ソースかけ (PDFファイル: 398.7KB)
令和5年度
若鶏のレモンソースかけ

給食のから揚げは、生姜醤油で下味をつけた鶏のもも肉にでん粉をまぶして油で揚げています。一般的には小麦粉をまぶして作った物を「から揚げ」、でん粉をまぶして作った物を「竜田揚げ」と呼ぶそうですが、あまり明確な分け方はしていないようです。下味も塩、胡椒だったり、にんにくやハーブを使う事もあります。今日のから揚げは、下味をつけて揚げた後にレモン風味のたれをかけてあります。少しサッパリ感をだした味付けです。
ちなみに「竜田揚げ」とは、から揚げについた片栗粉の白色と揚げた鶏肉の色合いが、奈良県の竜田川に流れる紅葉のようであることからつけられたといわれています。
若鶏のレモンソースかけ (PDFファイル: 331.1KB)
白菜のシチュー

白菜は、寒さが厳しくなるこの季節に一段と甘みが増しておいしくなります。白菜などの冬の野菜は、糖分を蓄えることで寒い冬の畑でも凍ってしまわないように身を守ります。白菜は、ほとんどが水分ですが、かぜの予防や免疫力を上げるビタミンCを始め、カリウムやカルシウムなどのミネラルやおなかの調子を良くする食物繊維も豊富です。
ほうれん草のごま和え

旬の野菜「ほうれん草」を主役にしたごま和えです。野菜はゆでるとかさが減り、食べやすくなります。リクエスト献立になるほど、子どもたちに人気のメニューですので、ご家庭でも作ってみてください。
八杯汁

「八杯汁」は福島県の郷土料理です。あまりにもおいしくて8杯はおかわりをしたくなるというところから「八杯汁」と名付けられたそうです。加須市と福島県の双葉町は、友好都市です。今から、12年前の3月11日に東日本大震災がありました。多くの人が被害に遭い、亡くなられた方も大勢います。加須市にも双葉町からたくさんの人が避難してきました。「東日本大震災があったことを忘れずに、もし困っている人がいたら助け合う心を忘れないでほしい」という願いがこもった献立です。
シンガポールビーフン

ビーフンは米粉を50%以上使用し麺状に加工したものです。漢字にすると「米粉」と書き、もともとは閩南語(ビンナンゴ:広義で福建省南部、台湾、シンガポールなどで話される言語)でお米の麺を「ビーフン」と発音することから、日本でも同じ呼び名が広まりました。
ビーフンは、さまざまな具材や味付けとも相性がよく、和洋中問わず、炒め物や汁物、和え物として食べられています。
トックスーフ゜

「トック」は韓国のおもちです。韓国ではスープのことを「クッ」というので「トックク」と呼ばれています。日本のおもちは「もち米」で作るので、煮たり焼いたりすると、とてもよく伸びます。一方、韓国の「トック」は「うるち米」という、みなさんが普段ごはんで食べているお米で作られています。そのためスープに入れてもそれほど伸びず、形も変わりません。
にんじんシリシリ

にんじんシリシリは、沖縄県の家庭料理で、「にんじんシリシリー」とも呼ばれています。「シリシリー」という不思議な名前は、にんじんを切る(おろす)専用の「シリシリ器」という道具を使うからとか、切る時の動作や音からそう呼ばれるようになったといわれています。暑い時期でもにんじんをたくさん食べられる料理です。
レバーとポテトのオーロラソースあえ

レバーには体を作るもとになるたんぱく質や、血液の中で大切な役割である鉄分が多く含まれています。鉄分が足りなくなると貧血という病気になり、つかれやすくなったり、めまいを起こしたりします。レバーには独特のにおいがありますが、しっかり下ごしらえをして油で揚げるとあまり気になりません。ケチャップとソース、砂糖で作ったオーロラソースであえています。
レバーとポテトのオーロラソースあえ (PDFファイル: 429.8KB)
ビビンバの具

ビビンバは韓国の代表的な料理のひとつです。「ビビン」が「混ぜる」、「バッ(パッ)」は「ご飯」の意味で、ご飯にナムル(もやしや山菜をごま油で和えたもの)と卵や肉をのせて、コチュジャン、ごま油などお好みの調味料とよく混ぜて食べます。韓国では、家庭にある材料で手軽に作るものから、屋台や専門店で提供されるものなど、さまざまな種類のビビンバがあります。
ポテトきんぴら☆NEW!!☆

「新じゃが」が、おいしい季節になりました。じゃがいもに含まれる栄養素といえば、炭水化物と思う人が多いと思いますが、実はビタミンCも豊富です。その量は、みかんに匹敵するほどで、熱に壊れにくい性質があります。旬のじゃがいもを、上手に活用していきたいですね。
子どもたちにも人気のメニュー「ポテトきんぴら」を、おうちでも作ってみてください。
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育部 学校給食課(加須学校給食センター)
〒 347-0052
埼玉県加須市町屋新田1144番地1
電話番号:0480-68-3755 ファックス番号:0480-68-3243
メールでのお問い合わせはこちら





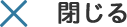

更新日:2025年12月23日