令和7年度施政方針
令和7年2月14日(金曜日)
1 市政運営の基本的な考え方
初めに、私の市政運営の基本的な考え方について申し上げます。
私が市長に就任して以来、間もなく3年が経過しようとしていますが、私の市政運営の基本は「継承」と「革新」、目指すまちづくりのキーワードは3つ「安全」「安心」「未来」、これは一貫しています。そして、「かぞ愛」をモットーに、全力疾走を続けています。
「継承」とは、第2次加須市総合振興計画を着実に推進することであり、「革新」とは、既存の方法などを改良し、進化させ、新しいアイデアを導入することにより、効率的かつ効果的に進めるプロセスのことです。
財政運営においては、「収支の均衡」「債務残高の圧縮」「将来への備え」の3つを堅持し、中長期的な視点を持ちながら、安定した運営をしていくことを基本としています。
また、限りある経営資源の中で行政サービスを拡充し続けることは不可能です。「あれもこれも」ではなく、「あれかこれか」という考え方の下に、優先順位を付け、必要な取組に注力する「選択と集中」による財政運営を今後も継続してまいります。
2 令和7年度の市政の基本方針
続きまして、令和7年度の市政の基本方針について申し上げます。
これまでの3年間を振り返りますと、利根川をはじめとした河川の治水対策はもとより、不幸な事故をきっかけに幹線用排水路や通学路に接した水路の安全点検とフェンス設置などを行った安全対策、市内全域の倒木リスクの高い危険樹木の伐採、全ての公共施設の安全点検と安全対策など、市民の皆様の「安全」を守る取組は最優先に、その時々の課題にスピード感を持って取り組んでまいりました。
また、こども医療費の対象年齢18歳までへの引上げ、こども食堂・フードパントリーについては加須モデルといわれる県内初の団体のネットワーク化の支援、がん検診やワクチン接種の助成の大幅な拡充、物価高騰対策として3年連続の学校給食費の5箇月免除など、市民の皆様の「安心」を支える取組を充実してまいりました。
さらに、不動岡小学校の大規模改修や元和小学校の増築、市内で創業・起業する人の支援制度の創設、貴重な財源を確保するふるさと納税の飛躍的増加、幼稚園・保育所の再編や小中学校のあり方の検討への着手など、希望の「未来」へとつなぐ取組にも挑戦してまいりました。
来る令和7年度は、私の市長としての任期4年間のうち、実質的な最終年度でもあります。
これまでに培った知識や経験を生かし、これまで注力してきた取組に更に磨きをかけながら、私の考える市長の役割を果たしてまいります。
市長の役割は3つあります。
1つ目は、ビジョンを示し、旗を振る役割です。
市の最上位計画である総合振興計画の後期基本計画をはじめとした様々な計画の策定や改訂が予定されています。これは加須市の「未来」への道しるべとなりますので、しっかりと取り組んでまいります。
剣豪・宮本武蔵は「五輪書・水の巻」において「遠き所を近くに見、近き所を遠くに見ること」が大切であると記しています。これは、目先のことにとらわれずに物事を俯瞰(ふかん)して状況全体を見ることの重要性を訴えています。
それぞれの計画の策定や改訂に当たっては、現状を踏まえるとともに将来を見据え、様々な視点から検討し、加須市の希望の未来を描いてまいります。
2つ目は、課題を市民の皆様と共有して、解決策も含めてアピールしていく役割です。
高齢化対策や子育て支援、防災対策、公共施設の再編や老朽化対策、かぞ版スーパーシティやDXの推進など、課題は山積しています。これらの難しい課題を市民の皆様と共有し、その解決策をアピールしながら、着実に取り組んでまいります。
例えば、数多くある公共施設の課題につきましては、令和6年度の施政方針で取り上げたほか、会議やイベントなどで話をしたり、広報紙に掲載するなど、積極的にお知らせしてまいりました。適切な公共サービスの提供と安定した財政運営を両立させるため、方針が定まった施設から順次対応策を示し、公共施設の最適化を着実に進めてまいります。
3つ目は、老若男女全ての市民がいつもどおり暮らせるように支援する役割です。
シニアも若者も、子育て世代も、障がいのある方もない方も、およそ赤ちゃんからお年寄りまで、全ての市民の暮らしを守り、支えていくためには、あらゆる分野、あらゆる課題に向き合う必要があります。「安全」も「安心」も全ての取組は「未来」へとつながります。引き続き、全方位戦略でまちづくりに臨んでまいります。
置かれている環境と与えられている条件の中で、全ての市民の暮らしを支えるためには何が必要かを常に考えながら、合理的な「判断」と問題を先送りしない責任ある「決断」を持って、総合振興計画を着実に推進する「継承」に、時代の変化に対応した「革新」を加え、全ての施策・事業を常にアップデートしながら、希望の「未来」に向かって全力で取り組んでまいります。
3 令和7年度予算案の概要
続きまして、令和7年度予算の概要について申し上げます。
予算の編成に当たりましては、令和6年度に引き続き、より丁寧な予算査定や財政調整基金を活用した歳入確保などに留意し、全ての経費について年間を通じた予算とすることを方針としました。
また、このたびの予算編成は、直近の決算である令和5年度決算における経常収支比率94.6%が示すとおり財政が硬直化する中で、長引く物価高騰や賃金・労務単価の上昇に加え、本市においては公共施設のマネジメントに関する経費の増加等もあり、各部からの予算要求時の予算総額では歳入と歳出のギャップが過去最大となるという非常に難しいものでした。
「全方位戦略」を前提としつつ、「選択と集中」により収支の均衡を図るため、年末から年明けまで連日のように議論を重ねてまいりました。
このようにして編成した令和7年度予算は、「安全・安心・未来のまちづくりを実現する予算」です。
その予算総額は、一般会計が前年度比10.5パーセント増となる過去最大の472億900万円、特別会計が前年度比4.0パーセント増の259億4,881万円、企業会計が前年度比2.0パーセント増の88億504万3千円、そして、これらを合わせた全会計では前年度比7.4パーセント増となる過去最大の819億6,285万3千円となりました。
4 令和7年度の主要施策
令和7年度予算の内容につきましては、この場で全てを説明することはできませんので、主要な施策の一部について、「安全」「安心」「未来」のキーワード別に、新たな取組や拡充する取組を中心に御説明申し上げます。
(1)「安全」
キーワードの1つ目、「安全」には、防災や防犯、交通安全などに関する施策があります。そのうちのいくつかの取組について申し上げます。
まず、「防災対策」に関する取組です。
昨年の出来事を振り返るとき、最初に浮かんでくるのは能登半島地震です。この地震では、木造住宅や上下水道の耐震化、避難所の環境改善など様々な課題が浮き彫りになりました。
「安に居て危を思う、思えば則ち備え有り、備え有れば憂い無し」という言葉があります。これは、順調な時にこそ将来の危機を思い起こすべきであり、警戒心があってこそ準備することができ、有事に危機を避けることができるという意味であり、平時における備えの重要性を説いた防災や危機管理の心構えを表す故事成語です。どんなに備えても憂いが無くなることはないのかもしれませんが、平時に危機を想像できる想像力と、その危機への具体的な備えが、被害を小さくするためには必要です。
そこで、震災から市民の命を守るため、木造住宅の耐震補助制度を大幅に拡充します。
また、耐震性の低い水道管である石綿セメント管の更新を加速します。
さらに、内閣府から令和6年12月13日に通知された避難所に関する取組指針・ガイドラインの改定を踏まえ、食料や生活必需品などの災害備蓄品の品目や数量を見直し、計画的な備蓄を進めます。
また、令和11年5月末をもって終了することとなってしまった現行の防災行政無線に代わる新たな災害情報伝達手段を整備するための基本設計を実施します。
また、平成10年から稼働し、北川辺地域を浸水の被害から守り続けている北川辺排水機場について、県営事業による大規模な修繕を実施します。
また、24時間365日昼夜を問わず市民の安全安心を守っている消防団、その第1分団の老朽化した詰所を新築します。
さらに、事業の進捗に伴い新たなまちが形成され、子育て世帯が増加している野中土地区画整理事業区域内の暫定供用中の調整池について、本整備を行います。
次に、その他の「安全」に関する取組について、いくつか申し上げます。
本市においては自転車による負傷事故が増加傾向にあることを踏まえ、新たに自転車用ヘルメットの購入を補助します。
また、いつでも身近な場所でAEDによる迅速な救命活動を行うことができるよう、包括連携協定を締結している市内のセブンイレブン全店にAEDを設置します。
「安全」「安心」「未来」の3つのキーワードの中で、市民の皆様の大切な命を守る「安全」は最優先です。様々な対策にスピード感を持って取り組んでまいります。
(2)「安心」
キーワードの2つ目、「安心」には、福祉、健康、子育て、教育、環境、文化・スポーツなど様々な分野に関する多くの施策があります。そのうちいくつかの取組について申し上げます。
まず、「子育て支援」に関する取組です。
妊産婦の経済的負担を軽減するため、医学上の理由等により遠方の分娩(べん)取扱施設で出産する際の妊婦の交通費や宿泊費を新たに助成するとともに、退院後の母子の心身のケアや育児サポートを行う産後ケアの利用料の減免支援を拡充します。
また、就学前のこどもの発達に関する困りごとに対応するため、新たに心理士による個別相談を実施します。
また、ヤングケアラーへの支援を強化するため、新たにヤングケアラー世帯への訪問支援を開始します。
また、民間保育所における保育士の人材確保につなげるため、職員の処遇改善に係る補助額を大幅に増額します。
さらに、志多見保育園の施設の老朽化に伴う大規模改修を支援します。
このように、本市の特徴でもある妊娠から出産、育児に至るまでの包括的な子育て支援につきましては、より一層の磨きをかけてまいります。
次に、「教育環境の充実」に関する取組です。
公立幼稚園において、保護者のニーズに応えるため、3歳児の預かり保育を全園で実施するとともに、長期休業日の預かり保育を1園で試行的に実施します。
また、本市の大きな課題である英語の学力向上を図るため、夏休みに実施しているイングリッシュサマーキャンプの対象を拡大するとともに、新たに市立中学校の生徒を対象に英検の検定料を助成します。
また、医療的ケアを必要とする生徒が安心して学校生活を送れるよう支援するため、新たに医療的ケアを行うことができる看護師を学校に配置します。
また、小学校の水泳指導の民間委託について、民間スイミングスクールとの調整が図れたことから、現在の6校から14校に拡大します。
また、教職員の業務負担を軽減するスクール・サポート・スタッフについて、年度当初から小学校全22校に配置します。
さらに、令和2年度末に整備した各小中学校で使用しているタブレット端末を更新します。
このように、未来を担う大切なこどもたちの学びを支える教育環境につきましては、課題やニーズに対応し、充実を図ってまいります。
次に、「健康・医療・スポーツ」に関する取組です。
令和8年度に開催予定の「ねんりんピック彩の国さいたま2026」において、本市がグラウンド・ゴルフの会場地となったことから、実行委員会の設立などの開催準備を進めます。
また、介護施設等でボランティア活動を行った高齢者にポイントを付与し、一定のポイントに達した方に絆サポート券を交付するシニアボランティアポイント事業を開始します。
また、認知症の早期発見と状況に応じた適切な治療につなげるため、新たに70歳の方を対象とする認知症検診を実施します。
また、帯状疱疹(ほうしん)ワクチン接種の定期接種化に伴い、帯状疱疹や合併症による重症化を予防するため、新たに帯状疱疹ワクチンの接種費用を助成します。
さらに、こどもから高齢者まで多世代がスポーツに親しみ、健康の増進や交流の活性化を図るため、平成国際大学が主体となって設立する新たな総合型地域スポーツクラブの運営を支援するとともに、新たにボールゲームフェスタを開催します。
このように、相互に関連し補完し合う健康、医療、スポーツの取組を充実することにより、市民の皆様の健康を増進し、日常生活の満足度や幸福度を高めてまいります。
次に、その他の「安心」に関する取組について、いくつか申し上げます。
「人はパンのみにて生くるにあらず」、これは聖書の一節です。人が豊かな人生を送るためには、文化・芸術の振興が必要なことはいうまでもありません。
また、長引く物価高騰の対策として、4年連続となる学校給食費5箇月分の一時免除を実施するとともに、学校給食費の保護者負担を増やさずに質と量を維持するための賄材料費の支援と、地産地消を推進するための地場産野菜等の購入費の支援を継続します。
また、害鳥獣による市民の生活環境被害を防ぐため、イノシシに対しては箱罠(わな)の設置や忌避剤等の防除対策を強化し、ムクドリに対しては新たに鷹匠(たかじょう)による追い払いを実施します。
また、ゼロカーボンシティを推進するため、民間活力を活用して公共施設等への電気自動車用充電設備の増設を進めます。
また、民生委員の負担軽減や担い手確保を図るため、活動を支援する交付金を増額します。
さらに、人生の最期に備え、誰もが自分らしく生きられるよう、新たに終活支援を実施します。
(3)「未来」
キーワードの3つ目、「未来」には、かぞ版スーパーシティ、産業や観光の振興、公共交通、人権・男女共同参画、DXの推進など幅広い分野の施策があります。そのうちのいくつかの取組について申し上げます。
まず、希望の未来の実現に向けた「計画の策定や改訂」の取組です。
現状や課題を明らかにし、明確な目標や将来ビジョンを共有することにより、計画的かつ効率的で効果的な市政運営へとつなげていくため、総合振興計画の後期基本計画や、本市で初めてとなる都市計画マスタープランの策定に加え、23の部門計画の策定や改訂を行います。
次に、「公共施設マネジメント」に関する取組です。
今後の小中学校のあり方については、教育総務課内に専任組織「魅力ある学校づくり推進室」を新設する体制の強化を図り、教育委員会において、望ましい学校規模等を示す基本方針を策定し、その後、再編等を行う学校や時期を定める基本計画の策定に着手します。
また、加須市学校施設長寿命化計画に基づき、礼羽小学校の長寿命化改良工事と高柳小学校の長寿命化改良工事設計、加須西中学校の構造躯(く)体劣化状況等調査を実施します。
さらに、教育環境の更なる向上と防災機能の強化を図るため、災害発生時には地域住民の避難場所としての役割も果たす中学校全8校の体育館等への空調設備の整備に着手します。
また、今後の保育ニーズを踏まえ、旧耐震基準で建築された老朽化が著しい第一保育所と第四保育所を統合し、令和9年度の開所を目指して、新たな保育所を整備するための調査・設計を実施します。
また、市役所本庁舎については、令和4年度に実施した劣化等調査の結果を踏まえ、老朽化した設備を順に改修しており、照明器具のLED化、給排水及び衛生設備の更新等を順次実施します。
また、加須クリーンセンターごみ焼却施設の長寿命化を図るため、令和9年度及び令和10年度に予定している大規模な基幹改良工事の基本設計を実施します。
また、公園の安全性や利便性の維持向上を図るため、騎西総合公園、星子沼公園、かくれんぼ公園の設備等の整備を行います。
また、昨年9月のテレビ放送で話題になった加須未来館については、クラウドファンディングを活用し、展示品の刷新、機材の更新等により魅力アップを図る「加須未来館リニューアルプロジェクト」を始動します。
さらに、平成29年度から実施している川口地区公共下水道管渠(きょ)整備工事を完了させます。
このように、数多くある公共施設につきましては、維持・補修だけでなく、施設の状況に応じて、廃止や統合、更には長寿命化やリニューアル、新設など、多様な対応を段階的に進めてまいります。
次に、「かぞ版スーパーシティ」に関する取組です。
加須駅周辺の新たなまちづくりにつきましては、優先的まちづくりゾーンの事業化想定区域への都市機能の集積に向けて着実に取り組みます。
まず、具体的な公募条件を精査するため、進出希望のある事業者への意向確認を継続するとともに、新たな事業者への意向調査を含めた情報収集を行います。
また、公募の前提の一つとなる道路整備については、現地測量や権利調査、概略設計に着手します。
また、調整池を含む公園の整備については、基本構想の策定に着手します。
さらに、加須駅北口の中心市街地の活性化に向け、地域の皆様から意見を伺う場を設けます。
このように、民間事業者の進出意向確認やインフラ整備等を同時に進め、早期の実現を目指してまいります。
次に、「産業や観光の振興」に関する取組です。
こどもたちが宇宙に関心を持つきっかけづくりや地域の活性化につなげるため、本市出身者が代表を務める民間宇宙関連会社と連携して、加須産米をロケットで宇宙空間に送る「宇宙米プロジェクト」を推進します。
また、昨年、農作物に大きな被害を与えたカメムシ等への対策として、農業者が実施するカメムシ等の防除薬剤の散布に係る費用を助成します。
また、次世代の農業を担う人材の一層の呼び込みと定着を図るため、新規就農者が円滑に就農できるよう、研修や機械導入等の取組を支援します。
さらに、観光を取り巻く社会情勢や旅行に対する意識の変化に対応し、観光振興事業の更なる充実を図るため、加須市物産観光協会の法人化や公募による外部人材の採用といった協会組織の見直しを支援します。
本市の基幹産業である農業はもとより、工業や商業も含めた産業全体の維持発展や観光推進体制の強化などに取り組み、魅力と活力にあふれるまちを目指してまいります。
次に、「DXの推進」に関する取組です。
本市の様々な地図情報をアナログからデジタルへシフトし、業務の効率化を図るとともに、それらの地図情報をインターネット上に公開することにより、市民サービスの向上と窓口負担の軽減を図るため、統合型・公開型GISを導入します。
また、限られた財源や人的資源の中で、効果的かつ効率的な行政運営につながるペーパーレス化を更に推進するため、ペーパーレス支援ソフトを導入するとともに、電子決裁を含む文書管理システムの令和8年度稼働に向けた準備を進めます。
また、令和5年度から準備を進めてきた自治体情報システムの標準化については、対象システムの切り替えを完了し、標準準拠した20のシステムの利用を順次開始します。
さらに、戸籍法等の改正により、戸籍に氏名の振り仮名を記載することに伴い、本人への通知や届出された振り仮名の入力作業、コールセンターの設置などを行います。
このように、様々な分野にデジタル技術を導入し、市民サービスの向上や業務・働き方を改革するDX(デジタル・トランスフォーメーション)を推進してまいります。
次に、その他の「未来」に関する取組について、いくつか申し上げます。
「陰徳善事」という言葉があります。これは、人知れず良い行いをするという意味ですが、今や、「いくら素晴らしいものを作っても、伝えなければ無いのと同じである。」というアップルの創始者スティーブ・ジョブズの言葉に象徴されるように、あらゆることを情報発信する時代になりました。こうした変化に対応し、より効果的なプロモーションを図るため、外部専門家による現行施策の分析・評価や、職員の要点をまとめる力・伝える力などを高めるプレゼンテーション能力向上研修を実施します。
また、差別や偏見のない人権尊重社会を実現するため、市の全ての施策において常に人権尊重の視点に立って取り組むとともに、市民の人権意識の高揚を図る人権教育や人権啓発を推進します。
さらに、身近な方が亡くなられた際の様々な手続をワンストップで受け付け、御遺族の不安や負担を軽減する「おくやみコーナー」を設置するとともに、市民の利便性向上を図る「書かない窓口」については、設置に向けた具体的な検討を進めます。
以上、令和7年度の主要施策について申し上げました。これらの取組を中心として、全ての事業に全力で取り組んでまいります。
5 結びに
結びになりますが、本年3月23日、本市は合併15周年を迎えます。
これまで本市の発展に御尽力いただきました多くの先達、議員各位、市民や事業者の皆様には、敬意を表しますとともに、心より感謝を申し上げたいと思います。
この節目を迎えるに当たり、多数の応募の中から決定した本市の新たなキャッチコピーが「笑うかぞには福来る」です。
既に暦の上では春となり、これからたくさんの美しい花々が私たちの目を楽しませてくれます。花が咲くことを「花が笑う」と表現することがありますが、「咲」という漢字と「笑」という漢字は、もともとは同じ文字であったといわれています。花も人も一番美しいのは笑顔のときだと思います。
至る所に笑顔があふれ、住む人々に幸せが訪れるような加須市の「未来」に向けて、本年も議員各位や市民の皆様のお力添えをいただきながら、「かぞ愛」を持って、全力疾走してまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課(本庁舎3階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
メールでのお問い合わせはこちら





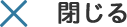

更新日:2025年02月14日