児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚や父または母の死亡などによって、ひとり親となった家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
手当の支給を受けることができる方
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(20歳未満で一定の障がいがある児童を含みます。)を育てている父または母若しくは主として生計を維持する養育者
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母に一定の障がいがある児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父母ともに不明である児童
(注1)婚姻には、事実上婚姻関係と同様の状況にある場合(内縁関係など)を含みます。
(注2)次のいずれかにあてはまる場合は、手当の支給を受けることができません。
・申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき(母子生活支援施設などを除く。)
所得制限について
受給資格のある方は、所得の額にかかわらず申請できます。ただし、申請する方やその配偶者、生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当が支給停止となる場合があります。
下の表の所得限度額未満の場合に、全部支給または一部支給となります。
| 税法上の扶養人数 | 全部支給(本人) | 一部支給(本人) | 配偶者・扶養義務者 孤児等の養育者 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
| 1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
| 2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
| 3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
| 4人 | 2,210,000円未満 | 3,600,000円未満 | 3,880,000円未 |
手当の額(月額)
受給資格者本人の所得の額と児童の人数により手当の額は異なります。
令和7年度の児童扶養手当額については、下表のとおりです。
| 児童の人数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人の場合 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
| 2人目の加算額 (1人の場合の額に加算する額) |
10,750円 | 10,740円~5,380円 |
| 3人目以降の加算額 (1人の場合の額と2人目の加算額を合わせた額に加算する額) |
10,750円 | 10,740円~5,380円 |
| 児童の人数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人の場合 | 46,690円 | 46,680円~11,010円 |
| 2人目の加算額 (1人の場合の額に加算する額) |
11,030円 | 11,020円~5,520円 |
| 3人目以降の加算額 (1人の場合の額と2人目の加算額を合わせた額に加算する額) |
11,030円 | 11,020円~5,520円 |
手当の支給月
手当は、年6回、5月(3月・4月分)、7月(5月・6月分)、9月(7月・8月分)、11月(9月・10月分)、1月(11月・12月分)、3月(1月・2月分)の各支払月の11日(その日が金融機関の休業日にあたる場合はその直前の営業日)に指定された口座に振り込みます。
手当の支給を受けるための手続き
手当の支給を受けるためには、市に認定請求を行う必要があります。手当をさかのぼって支給することはできませんので、請求事由が発生したら速やかにご相談ください。
手続きには次のものをご用意ください。
- 請求者と児童の戸籍謄本(父母の離婚等の請求事由及び該当年月日が確認できるもの)
- マイナンバーがわかるもの(通知カードまたはマイナンバーカード等:請求者、児童及び扶養義務者)
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 年金手帳
- 遺族年金等の公的年金を受給している方(申請中の方)は年金証書または年金支払通知書
- 請求者の口座番号がわかるもの
その他申請者の状況により必要な書類がありますので、必ずご本人が窓口にご来庁の上、ご相談ください。また、手続きには多少お時間がかかりますので時間に余裕をもってご来庁ください。
届出が必要な場合
次のような場合は届出が必要です。
- 受給者や児童の住所や氏名が変更になったとき
- 養育する児童が増えたときや減ったとき
- 受給者が婚姻したとき(婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の状況にある場合を含みます。)
- 児童が児童福祉施設等に入所することになったとき(母子生活支援施設などを除きます。)
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者や児童が公的年金を受けられるようになったとき
- 受給者や児童が亡くなられたとき
届出が遅れると手当の支給を受けられない月が生じたり、すでに支払を受けた手当を返還しなければならなくなる場合がありますので、ご注意ください。
現況届
受給資格者(全部停止中の方を含みます。)は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。案内を郵送しますので、指定する期間内に提出してください。この届を提出しないと11月分以降の手当の支給を受けられなくなります。また、現況届が2年間提出されない場合、手当の受給資格がなくなります。なお、一部支給停止除外事由に該当する方は現況届とともに提出してください。
一部支給停止措置について
児童扶養手当は、支給開始の月から5年または離婚等の支給要件に該当するに至った月から7年のどちらか早いほうが経過したときに、手当額の2分の1の支給が停止されることがあります。(児童扶養手当法第13条の3) その場合も、就業していることなどが確認できれば、以前と同様に手当を受給することができます。対象の方にはお知らせしますので、8月の現況届とともにお手続きをお願いします。提出期限を過ぎてしまうと、児童扶養手当額の2分の1が支給停止となりますので、ご注意ください。
児童扶養手当との公的年金の併給について
年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。該当する方は、子育て支援課へご相談ください。
児童扶養手当と障害年金の併給調整について
児童扶養手当の額が障害年金の子加算部分の額を上回る場合、その差額分を児童扶養手当として受給することができます。
また、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」には、非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。非課税所得である公的年金給付等を課税所得の公的年金等とみなし、公的年金等控除等を適用して算出した額を「所得」に加算します。
該当する方は、子育て支援課へご相談ください。
児童扶養手当に関するお問合わせ先
子育て支援課
- 子育て支援担当(本庁舎):電話 0480-62-1111
- 騎西福祉健康担当(騎西総合支所) :電話 0480-73-1111
- 北川辺福祉健康担当(北川辺総合支所):電話 0280-61-1204
- 大利根福祉健康担当(大利根総合支所):電話 0480-72-1317
この記事に関するお問い合わせ先
こども局 子育て支援課(本庁舎5階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471
メールでのお問い合わせはこちら





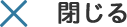

更新日:2025年04月01日